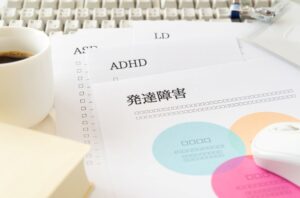急速に進むデジタル化や社会課題の複雑化に伴い、公務員にも新しいスキルが求められる時代が到来しています。これまでの知識や経験だけでは対応しきれない業務が増えるなか、キャリアの安定と成長のために「リスキリング(学び直し)」が注目されています。
特に資格取得は、専門性を高めるだけでなく、住民サービスの向上や組織内での活躍の幅を広げる大きな武器となります。
本記事では、公務員におすすめのリスキリング資格を10種類厳選し、それぞれの特徴やメリット、さらに資格を選ぶ際のポイントについて詳しく解説します。
公務員におすすめのリスキリング資格10選
公務員のキャリアを広げるには、実務に役立つスキルや新しい知識の習得が欠かせません。資格はその力を客観的に示し、住民サービスの向上やキャリアの安定にもつながります。
ここでは、公務員におすすめのリスキリング資格を10種類ご紹介します。
1.G検定
G検定(ジェネラリスト検定)は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施するAIに関する知識検定です。
ディープラーニングを中心とした人工知能の基礎を体系的に学べるため、AIの仕組みや活用事例を理解し、行政分野に応用する力を養えます。公務員にとっても、行政サービスのデジタル化や業務効率化を進める際に欠かせないスキルとして注目されています。
例えば、住民相談のデータ分析や、AIを活用した業務改善の企画立案など、幅広い分野で活かせるのが特徴です。また、デジタル社会の進展に伴い、AI人材への需要は今後ますます高まると予測されています。
資格を取得することで、公務員としての市場価値を高めると同時に、新しいキャリアの可能性を広げられる点も大きなメリットです。
2.ITパスポート
ITパスポートは、経済産業省が認定する国家資格で、情報技術に関する基礎的な知識を幅広く身につけられる点が特徴です。
システムやネットワーク、セキュリティといったIT分野に加え、経営戦略やプロジェクトマネジメントなどの知識も問われるため、デジタル化が進む行政現場において大いに役立ちます。
特に自治体や官公庁では、住民サービスのオンライン化や業務システムの刷新などDX推進の取り組みが加速しており、部署や職種を問わず評価されやすい資格といえます。また、合格率は例年およそ50%前後と比較的高く、未経験者や社会人にとっても挑戦しやすい点が魅力です。
基礎をしっかり押さえておくことで、IT活用の場面で自信を持って対応できるようになり、公務員としてのスキルの底上げやキャリアの安定にもつながります。
3.基本情報技術者
基本情報技術者試験は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する国家資格で、情報技術に関する基礎的な知識と技能を幅広く身につけられる登竜門的な試験です。
システム開発やアルゴリズム、ネットワーク、データベース、セキュリティなど、実務で必要となる分野を体系的にカバーしており、行政のデジタル化やDX推進を進めるうえで欠かせないスキルの証明となります。
ITパスポートよりも専門性が高いため、難易度はやや上がりますが、その分得られる評価も大きく、技術に対する理解度や実践力をしっかり示せます。特に自治体の情報システム部門や、デジタル化施策を担う部署で働く公務員にとっては、キャリア形成や業務効率化に直結する資格といえるでしょう。
ITの基礎を確実に固めておくことで、行政サービスの質向上や新たなプロジェクト推進にも大きく貢献できます。
4.MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)
MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)は、WordやExcel、PowerPointといった事務ソフトの操作スキルを客観的に証明できる国際資格です。
文書作成や表計算、プレゼン資料作成といった日常業務に直結する内容であり、公務員の事務処理効率を大幅に高めることができます。特に自治体や官公庁では、膨大なデータの管理や住民向け資料の作成、報告書の整備などにOfficeソフトを用いる場面が多く、資格を持つことで「業務を正確かつ効率的にこなせる人材」として高く評価されやすいのが特徴です。
試験は全国の会場で随時受験できるCBT方式を採用しており、独学でも学習可能なため、働きながらでも短期間で取得を目指せます。
実務に即したスキルを証明できるため、日々の業務改善はもちろん、異動や昇進などキャリアの幅を広げる上でも有効な資格といえるでしょう。
>>MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)に問い合わせる
5.日商簿記3級
日商簿記3級は、企業や自治体の会計処理に必要な基礎知識を身につけられる資格で、財務・会計業務やコスト管理に幅広く役立ちます。
仕訳や帳簿記入、試算表の作成といった基本的な会計スキルを習得できるため、予算の執行管理や決算処理など、自治体の事務業務に直結するのが特徴です。
公務員にとっては、財務課や会計課といった専門部署だけでなく、事業企画や政策立案においても数字に基づく判断力を養える点で大きなメリットがあります。また、簿記3級は会計の入門資格として位置付けられており、学習範囲が比較的コンパクトで取り組みやすいのも魅力です。
さらに、3級を取得した後は、より実務的な知識が問われる日商簿記2級や、中小企業診断士、公認会計士など経営・会計系の上位資格へのステップアップも可能です。
会計知識を身につけておくことで、数字に強い公務員として信頼を高め、キャリアの幅を広げることにつながります。
6.行政書士
行政書士は、官公庁に提出する各種許認可申請書類の作成や提出手続きの代理、契約書や遺言書といった権利義務・事実証明に関する書類作成、さらに行政不服申立ての代理などを行う国家資格です。
法律知識を基盤とした業務が中心で、行政手続きに関わる幅広い専門スキルを身につけられるのが特徴です。公務員にとっては、日常業務に直結する知識を体系的に学べるだけでなく、住民サービスの質向上やトラブル防止に役立つ点で大きなメリットがあります。
さらに、国家公務員や地方公務員として17年以上、または20年以上行政事務に従事していれば、試験を受けずに行政書士資格を得られる制度もあり、キャリアの延長線上で活用できる資格といえます。
将来的に独立や再就職を考える際にも強みとなるため、安定した公務員キャリアと新たなキャリアの選択肢を広げる一歩となるでしょう。
7.社会保険労務士
社会保険労務士(社労士)は、人事・労務管理や社会保険制度に関する専門知識を有する国家資格で、企業だけでなく行政の現場でも高い活用価値があります。
年金や健康保険、労働基準法などに基づく知識は、市町村役場の年金担当や健康保険課、人事課といった部署で直結して役立つのが大きな特徴です。
例えば、住民からの年金や社会保険に関する相談対応、職員の労務管理や就業環境の整備など、業務改善や住民対応力の向上に直結します。また、働き方改革や人口減少による社会保障制度の見直しが進む中で、制度を正しく理解し運用できる人材は今後さらに求められるでしょう。
公務員として専門性を高めると同時に、将来的には独立や再就職の選択肢としても活かせる資格であり、キャリアの安定と幅を広げるうえで非常に有用です。
8.FP(ファイナンシャルプランナー)
FP(ファイナンシャルプランナー)は、税金・保険・年金・資産運用など、生活設計に欠かせない幅広い知識を備えていることを証明できる資格です。
住民からの相談対応において特に強みを発揮し、年金や保険の制度説明、ライフプランに関するアドバイスなど、福祉や生活支援に関わる部署で大いに役立ちます。また、地域住民の暮らしを支える公務員にとって、家計や老後資金に関する知識は業務改善だけでなく、信頼を得るうえでも重要です。
資格は3級からはじめられ、徐々に2級、1級とステップアップしていけるため、学習を通じて段階的に専門性を高められるのも魅力です。少子高齢化や社会保障制度の複雑化に伴い、生活設計の相談ニーズは今後も増えることが予想されます。
FP資格を持つことで、公務員として住民サービスの質を高めると同時に、自身のキャリアや生活設計にも役立てることができるでしょう。
9.法学検定
法学検定は、憲法・民法・行政法などの基本法分野を体系的に学べる検定試験で、公務員試験の出題範囲とも重なるため効率よく学び直せるのが特徴です。
行政の現場では、住民対応や契約、条例運用など法律知識を前提とする業務が数多く存在しますが、法学検定を通じて基礎をしっかり固めておくことで、より正確で説得力のある対応が可能になります。さらに、法律知識を持つ人材は、政策立案やコンプライアンス関連の部署でも重宝されるため、異動やキャリアアップの際に強みとして働きます。
検定は初級から上級まで段階があり、自分のレベルに合わせて受験できるため、法律を基礎から学びたい人から専門性をさらに高めたい人まで幅広く対応可能です。
法律に強い公務員としてスキルを磨くことで、住民サービスの質を高めるとともに、キャリア形成においても大きなアドバンテージとなるでしょう。
10.年金アドバイザー
年金アドバイザーは、年金制度や社会保障に関する専門知識を有していることを証明できる民間資格で、住民からの年金相談に的確かつ専門的に対応できるのが大きな強みです。
自治体の窓口や年金関連部署では、制度が複雑で分かりにくいという声が多く寄せられますが、この資格を持つことで信頼性の高い説明やアドバイスが可能となり、行政サービスの質を一段と高められます。
また、年金や社会保障は国民生活に直結する分野であり、今後も需要が高まり続けることが予想されます。そのため、年金アドバイザー資格を持つ人材は配置転換や異動の際に有利になり、キャリアアップのチャンスを広げることにもつながります。
さらに、日常業務だけでなく、自身や家族の生活設計にも活かせる点もメリットです。専門性を備えた公務員として信頼を高めるうえで、取得を検討する価値の高い資格といえるでしょう。
公務員がリスキリングを行う必要性
社会や住民ニーズの変化にあわせ、行政の役割や求められるスキルも大きく変わってきています。デジタル化や地域課題の複雑化に対応するため、公務員にとってもリスキリングは避けて通れないテーマとなっています。
業務内容の多様化への対応
少子高齢化や地域課題の複雑化に伴い、公務員に求められる業務は年々広がっています。従来の定型的な事務処理に加え、福祉・防災・地域活性化など多様な分野で専門知識や新しいスキルが必要とされています。
DX推進とITスキルの重要性
行政サービスのオンライン化やデジタル化が進む中、システムやデータを活用する力は必須となっています。AIやデータ分析などの基礎を理解しておくことで、業務効率化や住民サービス向上に直接つなげることができます。
キャリア形成と市場価値の向上
終身雇用が揺らぐ時代において、公務員も安定だけに甘んじることはできません。リスキリングによって専門性を高めることで、異動や昇進時の強みとなるだけでなく、将来的なキャリアチェンジやセカンドキャリアの選択肢も広がります。
住民からの信頼向上
社会制度やテクノロジーが変化するなかで、最新の知識を学び直すことは住民への適切な説明やサポートにつながり、公務員としての信頼性を高めます。
公務員がリスキリング資格を選ぶ際のポイント
リスキリング資格を選ぶうえでは、いくつかの視点を意識することが大切です。ここでは、公務員が自分に合った資格を見極めるためのポイントを整理します。
業務や部署に直結する資格を選ぶ
公務員がリスキリング資格を選ぶ際には、まず自分の担当業務や所属部署との関連性を重視することが重要です。日々の業務に直結する資格であれば、学んだ知識をすぐに実務に活かすことができ、組織内での評価や信頼向上にもつながります。
例えば、人事や労務関連の部署であれば社会保険労務士の資格を取得することで、職員の労務管理や制度運用に強みを発揮できます。
一方、政策立案や行政文書作成に携わる部署であれば、法的な文書作成や手続きの知識を体系的に学べる行政書士が役立ちます。
キャリアや異動の可能性を踏まえて「どの業務で必要とされるか」を意識して資格を選ぶことで、日常業務の貢献度を高めるだけでなく、将来のキャリア形成にもつながります。
将来のキャリアパスを見据える
資格を選ぶ際には、目の前の業務だけでなく、将来のキャリアパスを見据える視点も欠かせません。自分の強みや関心を整理し、「どの分野で長期的に活躍したいのか」を明確にすることで、学ぶべき資格も自ずと絞り込めます。
例えば、福祉分野に関心があれば社会福祉士やFP、法務や政策立案に強みを持ちたいなら行政書士や法学検定といった選択肢が有効です。また、一部の資格は公務員としての職務経験があることで試験の一部免除や有利な受験条件が設けられている場合もあります。
自身のキャリアを土台にこうした制度を活用すれば、効率的に資格取得を進めることが可能です。将来を見据えた学び直しは、キャリアの安定と可能性の拡大を同時に叶える手段となるでしょう。
資格活用事例から検討する
資格を選ぶ際には、実際にその資格を取得している先輩や同僚の活用事例を参考にするのも有効です。どのように日常業務で知識を役立てているのか、キャリア形成にどのような効果があったのかを直接聞くことで、資格の実用性や取得後のイメージをより具体的に描くことができます。
例えば、簿記資格を持つ職員が財務課で決算処理を効率化したり、社会保険労務士の知識を活かして人事課で労務管理の改善に貢献したりといった事例は、資格取得を検討する際の大きな参考になります。また、活用方法を知ることで「せっかく取得したのに業務で使えない」というミスマッチを防ぐことにもつながります。
活躍している先輩の経験談から学び、自分に合った資格を選ぶことが、日常業務への定着とキャリアアップを両立させる近道となるでしょう。
まとめ|公務員もスキルアップのためにリスキリングに取り組もう
社会や住民ニーズが多様化・複雑化するなかで、公務員にも新しい知識やスキルを習得する「リスキリング」が強く求められています。行政サービスのデジタル化やDXの推進、福祉や労務など幅広い分野での専門性の強化は、日常業務の効率化だけでなく、住民からの信頼向上にも直結します。その手段として資格取得は特に有効であり、自分の能力を客観的に証明できるだけでなく、異動や昇進の際の強み、さらには将来的なセカンドキャリアの準備にもつながります。
資格を選ぶ際には、担当業務や部署との関連性、将来のキャリアパスとの整合性、学習にかかる時間や費用などを意識して検討することが大切です。実際に資格を活用している先輩の事例を参考にすれば、取得後の具体的な活用イメージも描きやすくなります。
まずは興味のある分野や身近な業務に役立つ資格から小さく学び直しをはじめてみましょう。その一歩が、公務員としての市場価値を高め、未来のキャリアを広げる大きな力となります。
公務員のリスキリングに関するよくある質問
Q.リスキリング支援制度は公務員でも利用できますか?
A.原則として、公務員は企業と雇用契約を結んでいないため支援制度の対象外です。
ただし、非常勤公務員で勤務時間や雇用保険加入などの条件を満たす場合は利用できるケースもあります。詳しくは所属先やハローワークに確認しましょう。
Q.リスキリングを取り組むにあたって、公務員はどのようなスキルが役立ちますか?
A.行政のDX推進に直結するITスキルや法令知識、正確な文章作成力は不可欠です。
さらに、政策を数値や根拠に基づいて実行する流れが強まっており、統計学やマーケティングの知識も重要視されています。これらを身につけることで、業務改善や住民サービスの質向上に大きく貢献できます。