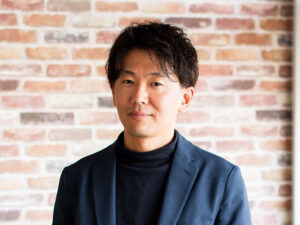株式会社プランノーツ代表取締役/
一般社団法人ノンプログラマー協会代表理事 高橋宣成氏
サックスプレイヤーから転身し、複数の企業でキャリアを重ねたのち起業家となった高橋氏。音楽家、会社員、そして起業 —— 異なる世界を渡り歩いて得た視点は、「働くこと」や「学び」の本質を鋭く捉えています。
少子高齢化やデジタル化、AIの急速な進化により、私たちの働き方やキャリアのあり方は大きく変化し、リスキリングの重要性が高まっています。しかし「何を、どう学ぶべきか」という問いに、明確な答えを持つ人は多くありません。
そんな中、高橋氏は「ノンプログラマー」のスキルアップを支援するコミュニティを運営し、数多くの人々のキャリア変革を後押ししています。
本記事では、そのユニークな経歴を辿りながら、ノンプログラマーのリスキリングの現状と、AI時代に求められる「学びのあり方」について伺いました。
サックスプレイヤーから転身――波乱のキャリアが起業の原点に
━━ サックスプレイヤーから会社員、そして起業に至ったご経歴を教えてください。
最初のスタートはサックスプレイヤーでした。親は団塊世代で「まずは会社に入って一生勤めるのが安定」という価値観が強かったです。でも、それにどこか反発する気持ちもあって。「もっと自由に生きたい」という想いから、音楽の道に進みました。
しかし、音楽業界で生計を立てるのは非常に厳しく、バブル崩壊後の影響もあって、ライブハウスやレコーディングの現場では仕事が減っていきました。テレビ番組でも生演奏が使われる機会が少なくなり、人件費の問題からレコーディングも簡素化されていきました。そうした厳しい現実を目の当たりにし、「このままでは難しい」と感じたのです。
そして30歳を機に、「やはり親の言う通り会社員が正解だったのかもしれない」と考え、会社勤めをはじめました。最初のうちは順調に働いていたのですが、あるIT企業在籍時に予期せぬ出来事が起きてしまいます。
役員間の内紛が勃発し、会社が分裂するという事態に直面したのです。その事件をきっかけに、社内ではリストラが行われ、150人いた社員が半数近くにまで減ってしまいました。私自身もマネージャーとしてたくさんの部下を解雇するという辛い経験をしました。
そして、「この会社で働き続けるのは難しい」と感じて36歳で転職を決意します。
しかし、この転職活動は非常に困難を極めました。それまでの会社では実績も出していたつもりだったので「なんとかなるだろう」と考えていたのですが、希望する管理職のポジションで、以前と同等の給与条件に合うところがなかなか見つからず、大変苦労しました。
そんな中、好条件で声をかけてくれた会社があったので、そこへの転職を決めたのですが、その会社がいわゆる “ブラック企業” でした。実現不可能な事業目標を課せられ、達成できないとひどく怒られる毎日。次々と同僚が辞めていく状況で、「このままでは本当に倒れる」と思い、半年ほどでやむなく再度転職することになりました。
再度、転職活動したときは、給料は気にせず、最低限生きられれば良いという条件でなんとか別の会社に転職できましたが、30代後半で家族もいたため、生活は本当にギリギリでした。
これから何十年も生きていかなければならない中で、「どうやって生きていこうか」と真剣に考えた時期でした。そして、そのときに起業を決意しました。
━━ 転職活動を経て起業を決意した背景には、どのような思いがあったのでしょうか?
ブラック企業の後に入社した会社も、少しブラックな側面がありました。これまで、親から「会社で働くのが幸せなんだ」と教えられ、サックスプレイヤーとしての失敗から「親の言うことが正しかった」と会社員になったにもかかわらず、結局このような境遇に何度も遭ってしまうという体験は、深い反省に繋がりました。
「みんながみんな同じような経験をするわけではないし、自分で考えて、自分で行動することが必要だ」と強く感じたのです。これから何十年も働き続けなければならないことを考えると、「そもそも働くとはどうあるべきなのか」を深く考える時期でもありました。
その結論のひとつが、起業です。当時、40歳前後での転職は非常に厳しくなるという年齢的なこともあり、「この選択肢しかない」という思いもありましたね。
ノンプログラマーの支援に込めた「働きを良くしたい」という信念
━━ 音楽業界ではなく、IT分野で起業された理由は何でしょうか?
大きな理由は2つあります。
1つ目は、これまでの転職活動で「プログラミングができますか?」と聞かれた経験が何度もありました。そのとき、ITスキルを持っていることは、キャリアにおける大きな強みになると実感しました。
2つ目は、4社目の会社での経験です。同僚がしんどそうに働いていて、よく見るとやっている仕事のほとんどがExcel作業でした。そのときに「Excelをもっとうまく扱うスキルを身につけて、それを自動操作するプログラミング言語を使えば、ここまで苦しまなくて済むのでは」と考えました。
つまり、ITを本職としていない人でもこうしたスキルを身につけることは、キャリア的にも、日々の実務を楽にする上でも、非常に大きな意義があると確信しました。私の事業のベースには、これまでの転職活動と会社員時代の経験が深く関わっています。
━━ 『ノンプログラマー』とは、どのような定義になるのでしょうか?
『ノンプログラマー』というのは、ITやプログラミングを本職にしていない人たちを指します。いわゆる『非IT職の人』です。ノンプログラマーを支援するというビジョンを描いたのは、「働くこと自体を良くしたい」という信念があったからです。
多くの方が、非効率な作業に時間を奪われてしまい、嫌々仕事をしている場面もあると感じています。そのため、プログラミング技術を活用して、業務を楽にできれば、多くの方の人生を豊かにできるかもしれないと思いました。
元々ITやプログラミングを本職にしている人たちは、自然とそうした技術を取り入れています。だからこそ、「そうではない人たち」つまり、ITの恩恵を十分に受けられていないノンプログラマーをサポートしようと決めました。
━━ 起業後のライフスタイル、ご家族と仕事のバランスはどう調整されましたか?
独立してから、仕事にあてる時間は増えました。しかし、その一方で独立によって自宅で仕事ができるようになり、家事・育児に割ける時間も増え、結果的にバランスの取りやすい環境を作ることができました。
家の中にいるので、「何かあれば自分も対応できる」という体制が取れるため、夫婦で協力して子育てできたのが良かったです。
また、私個人の特性としても、独立後の働き方は合っていました。会社員時代は、電車でオフィスに通うために「朝この電車に乗らなきゃいけない」「そのためには何時に起きなきゃいけない」といったことに、実はすごいストレスを感じていたと後になって気づきました。その点、今は自分でスケジューリングできるので、自分らしくいられるというメリットもあります。

リスキリングを阻む「固定観念」という名の壁
━━ 支援の現場で感じる、リスキリングや学びに関する壁はありますか?
IT分野に限らず一般的な学びに関しても共通して、『固定観念』つまり『バイアス』が最大の壁になっていると感じます。
『ラーニングバイアス』というものがあり、働く人たちの多くが「学習は若い人がやるもの」「学校でやるもの」と考える傾向にあります。
これは非常に大きな問題で、権限のあるポジションについている年齢層の高い方々が、このバイアスを持っているために、組織全体でのリスキリングが進まないというケースが多々あります。
しかも、これはITの進化と非常に相性が悪いです。IT技術は日々新しいものが生まれるため、本来であれば全世代が同じように学ぶ必要があります。しかし、年齢層が高い方ほど「自分はもう学ぶ必要はない」と考えてしまう傾向があるため、会社や組織として、新しい技術の導入や活用が非常に難しくなります。
『ラーニングバイアス』は複雑な感情になると思います。「今さら学んでも…」「自分にはできない」といった感情のほか、「これまでやってきた自分の成功体験を否定することになるのではないか」という感覚もあるかもしれません。
このように、働く人たちが持つ固定観念やバイアスといったものが、私たちが乗り越えるべき最大の敵、あるいは壁だと感じています。
━━ 実際に高橋氏のコミュニティに参加されているのは、どのような層の方が多いのでしょうか?
私が運営しているコミュニティのメンバーは、40代が多く、次いで30代、50代という感じです。60代や20代の方もいて、特定の世代に偏っているわけではありません。
40代が多い理由として、ひとつの仮説としては、キャリアの「踊り場」になりやすいということがあるかもしれません。30代では会社の直線的な戦力として働いていますが、40代に入って一度自身のキャリアを立ち返り、このままで良いのかと考えはじめる人が増えるのではないかと思っています。
AI時代における学びの進化と「本質」の見極め
━━ 近年のリスキリングの動向、特にAIの登場によってどのような変化が起きていますか?
これまでのプログラミングやITスキルは、ある程度、体系的に学べば誰でも習得できる「安定したスキル領域」でした。しかし、AIが出てきたことで、その構造が一気に崩れはじめたと感じています。
例えば、「それはAIに任せたほうが早い」という場面がどんどん増えていますし、逆に「AIを使う前提でどう学ぶか」を考え直す必要も出てきました。つまり、“何をどう学ぶか”をゼロから見直す必要がある時代になったということです。
実際、AIサービスの進化スピードはものすごく早いです。数ヵ月前に注目されていたツールが、気づけばGoogleなどの巨大プラットフォームが同様の機能を標準搭載しはじめて、そのツール自体が潰れてしまう、といったことが日常的に起きています。
━━ 激しく変化する中で、「本質的に残る学び」と「表層的な学び」をどう切り分けるべきでしょうか?
AIをはじめとしたテクノロジーが次々と登場してくる中で、「今それを覚える意味があるのか?」という見極めが必要になってきています。
例えば少し前に、ブームになったある「プロンプト術」がありました。みんな一生懸命それを覚えようとしていましたが、今はAIがユーザーの意図を汲み取って、それと同じことを勝手に「推論」してくれるように進化しています。こうした “表層的な学び” は、技術の進化によって簡単に陳腐化します。
ですから、今学ぼうとしていることは、時代が変わっても残り続けるものなのか、つまり”本質的な学び”かどうかを見極めるために、時代の情勢をつかむことや、情勢が変わったときに柔軟に適応していくことが求められると思います。
「仲間と学ぶ」越境学習がもたらす価値観の変容
━━ 学ぶ側の意識やモチベーション維持で重要なことは何でしょうか?
ノンプログラマーの方々を見て感じるのは、「1人で頑張らなきゃ」と思い込みすぎている人が多いということです。
『学ぶ=孤独な努力』というイメージを持っていて、受験勉強の延長線上で取り組んでしまいがちです。資格試験のような一発勝負の勉強ならまだしも、ITスキルやプログラミングのように“実践的に使う”ことが目的の場合、1人でやるメリットはあまりないです。
私のコミュニティでは、仲間と学ぶことをとても大切にしています。これは、学びの効果や効率を高めるという面もありますが、何よりもモチベーション維持に大きく関わります。
1人だと孤独で、分からないことがあっても周りに聞けず、挫折しやすい。多くの方がそうした経験をしてしまいます。
しかし、頼れる仲間と学べば、自分の知らないことは他の人が教えてくれます。教え合うことによって「こういう仲間がいるから自分も頑張ろう」という相乗効果が生まれます。このような『仲間と学ぶ』という学び方を知る経験が、今までなかった人が多いのだろうと感じています。
学ぶという行為には「1人でやるものだ」という固定観念が根強くありますが、ぜひ「仲間と学ぶ」という選択肢を入れてみてほしいです。
━━ コミュニティでの「越境学習」が、参加者のマインドセットにどのような影響を与えましたか?
コミュニティを通じて感じたのは、『越境学習』が人の価値観を大きく揺さぶるということです。元々「学びを共有し合う場」としてコミュニティをスタートしたのですが、結果的に“内面的な変化”が起きている方がすごく多いです。
例えば、従業員が数百人いる病院の院長さんがコミュニティに参加しましたが、「こんなに多くの人が生き生きと学んでいるんだ」と驚かれていました。そして、自分自身の学びに対する姿勢を見直すきっかけになったそうです。
これは、ある意味 “異文化に触れる体験” になります。普段の職場や環境から一歩違う世界に出て、全く違う価値観の人たちと関わることで、自分の固定観念が揺さぶられる。そういう経験を通じて、「学びとはこうあるべきだ」というバイアスが少しずつ解けていきます。
後から調べたところ、これは専門家からも実証されている『内面的な変化学習』という概念でした。あえてアウェイな環境に飛び込むことで、知識以外のものが得られる効果は非常に高いと実感しました。
クラウドワーカーが持つ「小さな強み」
━━ 企業に属する社員と、クラウドワーカーのリスキリングにおける違いは何でしょうか?
独立して個人事業主(クラウドワーカー)として活動する強みは、「自分ですぐに決定して物事を動かせる」という点にあると思います。これがリスキリングにおいて非常に有利に働きます。
例えば、AIや新しいITツールを会社に導入しようと思っても、一般企業であれば複数のハードルを超えなければならず、難易度が高いのが現状です。その点、個人であれば自分の判断ですぐに試せます。技術や新しい知識に “先に触れられる” という意味では、非常に有利なポジションにいると思います。
━━ 学習環境や心理的な要素は、ワーカーの成長にどのように関係するのでしょうか?
『ラーニングバイアス』など人の感情や考え方は、人との繋がりを通じて伝染すると言われています。
例えば、職場が「どんどん新しいことにチャレンジしよう」「積極的に学んでいこう」という環境であれば、自然と前向きな気持ちになりやすいです。しかし逆も然りです。
クラウドワーカーは、自身で環境をコントロールできるという大きなアドバンテージがあります。「誰とコミュニケーションを取るか」「誰と繋がっていくか」といった人間関係の設計を、自分で主体的に決められるからです。この大きなアドバンテージを活かして、自分の可能性を広げていってほしいです。

学びは「手段」であり、本当にやりたいことを見つけることが最優先
━━ 今後の事業展開や展望についてお聞かせください。
現在、ITプログラミングを中心とした学びのコミュニティを運営していますが、今後は全国へと広げていきたいと考えています。
ただ、私自身のコミュニティだけでは限界があります。そのため、会社や地域といった単位で「学びのコミュニティを自分でも作りたい」という人を増やしていきたいです。
例えば、社内コミュニティや地域コミュニティのように、身近な場所で気軽に学べる場があると、人はもっと学びやすくなります。いきなり知らない場所に飛び込むのは、誰でもハードルが高いですし、参加費がかかるとなると、さらに勇気が必要です。
しかし、「隣の席の同僚が勉強会をはじめたから行ってみようかな」といった距離感なら、ハードルが下がり、自然に参加できるのではと考えています。
━━ リスキリングに取り組むクラウドワーカーに向けて、メッセージをお願いします。
まず伝えたいのは、「学び」や「スキル習得」そのものが目的ではない、ということです。一番大切なのは、自分が本当にやりたいことを見つけること。スキルはあくまで“手段”であって、“目的”ではないです。
私自身、もし会社組織の中にいたら「それは儲からないからやめなさい」と言われるようなことを、今まさに自分の意志でやっています。でも「小さな単位だからできること」がたくさんあります。クラウドワーカーは、そうした “自由に動ける強み” をもっと活かしてほしいと思います。
やりたいことが明確になれば、自然と「これを学んだ方がいい」「このスキルを身につけたい」という気持ちが湧いてきます。そのとき初めて、リスキリングが自分の中で本当の意味を持つと感じます。
DXもAIもリスキリングも、すべては自分の思いを形にするための手段に過ぎません。だからこそ、焦らず『自分の軸』を見つけることを大切にしてほしい。その上で、自分の好きなことを追いかけながら、新しい技術や知識を取り入れていけば良いと思います。
まとめ
AIの進化により、必要なスキルやツールは驚くほどの速さで変化しています。
そんな時代に大切なのは「何を学ぶか」よりも「なぜ学ぶのか」。リスキリングの本質は、“自分の軸を見つけること”にあることが今回の取材で見えてきました。
環境に左右されず、自らの意志で学びを選び取れるクラウドワーカーは、まさに変化を味方につけることができる存在です。自分の強みを活かしながら、学び続ける姿勢こそが新しい価値を生み出します。
学びは手段であり、目的は「自分の思いを形にすること」。一人ひとりが自分のペースで学び、挑戦を重ねていくことで、未来の働き方はもっと自由で豊かになっていくでしょう。