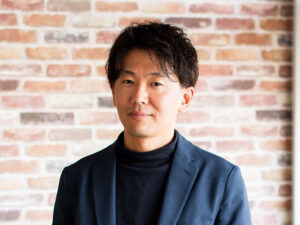学習院大学 経済学部 教授 守島基博氏
AIやデジタル化、グローバル化が進む現代において、働き方やキャリアの常識は大きく変わりつつあります。
企業は経営戦略の一つとして「人的資本経営」を掲げ、人材育成やスキル向上への投資を強化していますが、それだけでは企業変革は実現できず、個人にも「学び直し(リスキリング)」の必要性が高まっています。
今回は、人材マネジメントや人的資本経営を専門とし、大学教育の現場でも多くの学生を指導している守島氏に、リスキリングの重要性や今後のキャリア形成に必要な視点、そしてクラウドワーカーが自分らしく働くためのヒントを伺いました。

研究分野と教育現場から見る人材マネジメントの現状
━━ 現在の研究分野や注力されているテーマについて教えてください。
私の研究分野は企業における人材マネジメントや人事管理全般です。特に、最近は、エンゲージメントや戦略人事における人のマインドの役割など、従業員のモチベーションや働きがいを高めるための取り組みを研究テーマとしています。
大学では「人的資源管理」という授業を担当し、学部では基礎理論を中心に、大学院では研究者育成を目的に実践的な指導をしています。学部向けでは社会に出る前の段階で「働くこととは何か」という概念から理解を深めてもらい、大学院では研究データや企業事例を通じて、より専門的なマネジメント論を教えています。
━━ 社会人向けに講演などもされていますが、大学とどのような違いがありますか?
大きな違いがあります。大学生と言っても、2年生ぐらいまでは、ほんの少し前までは高校生であり、多くの場合アルバイト経験があるかないかくらいです。なので「働く」という行為そのものに対する現実感が薄い状況です。最初は家族からやテレビの情報を基にしたイメージしか持っていない学生も多く、人材マネジメントの概念は抽象的に感じられるようです。
しかし3年生になると就職活動が始まり、企業や働き方に対する関心が一気に現実味を帯びます。授業の中でも、「自分はどういう企業で働きたいのか」といった具体的な疑問を持つようになります。
一方、社会人向け講演では、すでに実務経験がある方々が対象となるため、より具体的で実践的な話を中心にします。人材評価やエンゲージメント向上策、人的資本経営の実践方法など、現場で直面している課題に即したアプローチが求められます。

企業で高まる「人的資本経営」とスキル需要の変化
━━ 近年注目されている「人的資本経営」について、どのような変化がありますか?
「人的資本経営」とは、従業員一人ひとりに投資をし、その価値を高めることで企業全体の価値を向上させる考え方です。ここ数年でこの考え方への関心が急速に高まり、経営戦略の中心に据えられるようになりました。
背景には大きく2つの理由があります。
1つ目は深刻な人材不足です。10~15年前までは資金不足で事業が停滞するケースが多かったのに対し、現在は「人がいなくて事業が回らない」というケースが多い状況です。そのため、多くの経営者が“人という資本または資源”を経営の中心に置くようになってきました。
2つ目は企業変革の時代に突入したことです。グローバル化、AI・ITの進展、DX推進などによって、これまでのやり方だけでは競争に勝てなくなってきました。新しい仕組みや価値を創造したりイノベーションを生み出したり変革できる人材が求められています。
こうした流れの中で、企業の外部にいる株主や投資家からも「人的資本」への興味関心が増えたのも一つのポイントです。従来から「企業は人なり」と言われるように人材は重要とされてきましたが、これまで以上に「人材確保や育成計画があるのか」といった点が企業評価の基準の一つになってきています。
少子化・AI時代に求められるキャリア戦略
━━ 少子化やAI・デジタル化によるスキル需要の変化について、どのようにお考えですか?
AIやITといったデジタル化に加えて、グローバル化が進み、今まで求められなかったスキルが働く人に求められるようになってきました。企業に雇用されて在籍していれば企業内研修やキャリアカウンセリングといった各種制度の下でスキルアップは図られますが、クラウドワーカーはそれがありません。企業は何を求めているのかを把握して、自らスキルアップしていく必要があります。
ただ、単純にスキルアップして自分の価値を高めるのではなく、どういうスキルを身に付けて活かしていくのかといった戦略を立てることも重要です。企業や業界の変化に合わせて方向転換する柔軟さが大事になります。「キャリアオーナーシップ」という意識に基づいて、自分のスキルの棚卸しはもちろんのこと、自分が持つ知識や経験を見直しながら「市場や企業が今求めている能力」を意識的に磨くことが、キャリアを継続的に発展させる鍵となります。
また、少子化による労働人口減少で人手不足は加速していますが、すべての職種で均一に不足しているわけではありません。一般事務職の求人には応募が集中する一方、専門職やデジタルスキルを持つ人材は依然として不足しています。
AIやITが進化し、標準化された業務や単純作業は自動化が進みます。その結果、人間には「課題発見力」や「柔軟な判断力」「コミュニケーション力」といった非定型スキルが求められるようになります。例えば、顧客対応の場面を考えると、シンプルな質問や問題解決は既にAIのチャットボットなどで対応できる。でも、顧客自身が気づいていない課題を見抜き、それを解決する提案ができる力はAIには難しい領域です。
日本社会におけるリスキリングの課題と展望
━━ 日本のリスキリング環境にはどのような課題がありますか?
日本は企業内教育が手厚い一方で、社会全体で個人がキャリアアップしたり、キャリア相談をできる場が極めて少ないという課題があります。アメリカではコミュニティカレッジや大学のキャリアセンターが社会人にも開放されており、キャリア相談からアップスキル講座まで一貫して、社会に開放されています。
一方、日本ではキャリアカウンセリングを受ける機会は限られています。国家資格を持つキャリアカウンセラーは7万人ほどいますが、専業として活動できている人は一部にとどまっているのが現状で、その多くが企業内で自社の社員にカウンセリングを行うのが、主な仕事です。もっと社会全体で、キャリア相談や実践的な学びの場を増やし、専門的なアドバイスを受けられる環境を社会全体で整備することが急務です。
さらに、働く個人の意識改革も必要です。学び直しやスキルアップが「自分の市場価値を高める行為」であるという認識を持ち、自主的に学ぶ姿勢を強化することが求められています。少し前までは、自己学習に当てる時間が平均月十数分程で、非常に短時間といった統計が出ていましたが、今では数時間単位と増えてきています。少しずつ各個人の意識も変わってきているのだと思います。
今後のトレンドとして、キャリアカウンセリングができる場面や、eラーニングのような学びやすい環境が増えてくることが予想されるでしょう。その背景として、従来は企業に長く在籍して熟練することが良しとされてきましたが、その分野がAI参入などによってなくなる可能性もゼロでないなどの可能性が出てきたことがあります。そのため、幅広く様々なスキルを身に付け、さらに更新してくことが求められ、そうした機会が増えていくと思われます。
また転職が一般的になってきたことも背景の一部なのかもしれません。ただ役職や職歴だけではなく、どんなことをしてきて何ができるのか等の具体的スキルを職務経歴書で示せるのかが要請されるようになり、スキルを棚卸し、明確化することへの意識が増えてきたのだと考えられます。
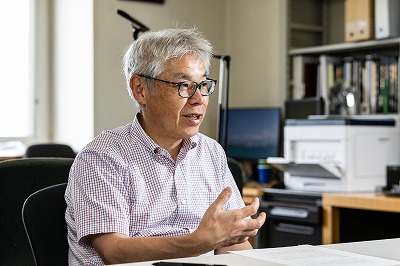
クラウドワーカーへのメッセージ:自由を活かすための学び直し
━━ クラウドワーカーに向けて、アドバイスをいただけますか?
クラウドワーカーは企業の枠に縛られず、自分の裁量でキャリアを築ける自由があります。いわば自分の人生をマネジメントしコントロールすることが可能です。しかしその一方で、企業の教育システムに頼れない分、自ら情報収集やアップスキルの機会を確保する必要があります。
自由には責任が伴います。AIやテクノロジーが急速に発展する時代において、人間にしかできない価値提供 ──たとえば顧客の潜在的な課題を見抜き、解決策を提案する力や、信頼関係を構築するコミュニケーション力など── がより一層重要になります。
キャリアプランを自分で描き、その実現に向けた自分のための自分によるリスキリングを計画的に行うことで、クラウドワーカーは自らの価値を高められます。企業に属さないからこそ、自分の市場価値を意識し続けることが、自由を最大限に活かすための鍵となります。
まとめ
従来の「企業に長く勤める」だけのキャリアモデルは過去のものになりつつあります。学び直しは一部の人のためではなく、すべての働く人に必要な「人材としての価値向上の手段」です。
守島氏は「キャリアの自律と主体的な学びこそが、自由と安定を両立させる武器になる」と強調します。AIやデジタル化の進展に伴った“変化の時代”を生き抜くためには、自らの意志でキャリアをデザインし、学びを積み重ねていく姿勢が不可欠と述べる。
これからの時代、リスキリングは単なるスキル習得にとどまらず、「自分の人生を自分でコントロールするための手段」として、その重要性が増していくでしょう。