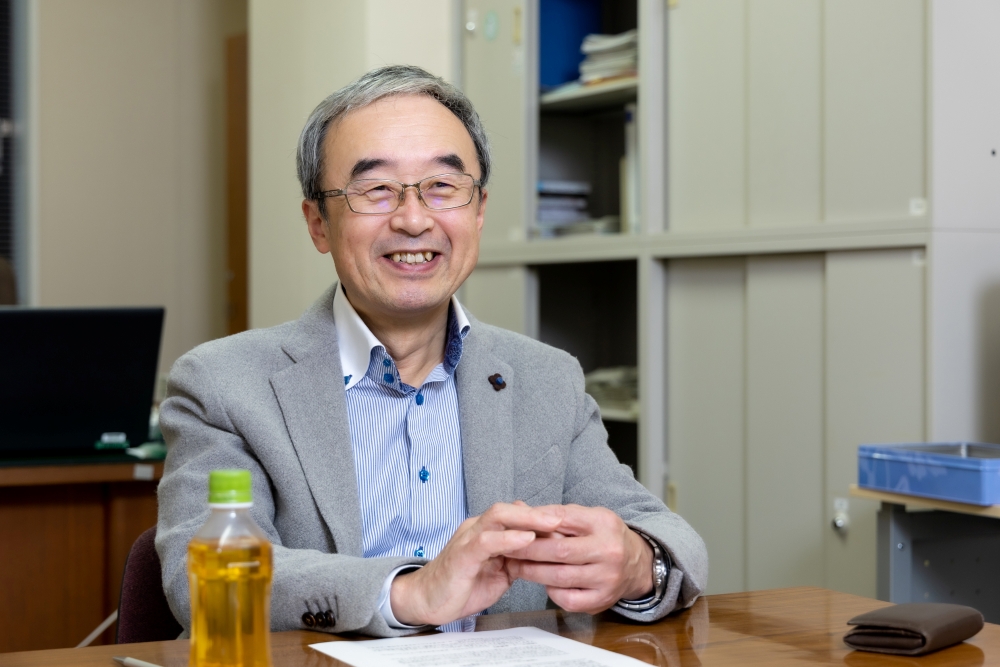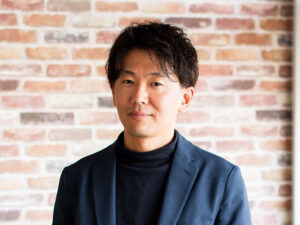多摩大学大学院 名誉教授/株式会社ライフシフト 会長 CEO 徳岡晃一郎氏
少子高齢化や人口減少、急速なデジタル化が進む中、私たちの働き方やキャリアの常識は大きく変わりつつあります。
こうした時代において必要とされるのが学び直し(リスキリング)であり、より広い視野で社会課題に挑む「イノベーターシップ」の能力が求められます。
大学教育と企業経営の両面で人材育成に取り組む徳岡氏に、人生100年時代に向き合う姿勢やリスキリングの重要性について伺いました。
キャリア設計と社会貢献を両立するライフシフト
━━ 現在、研究や実務で注力されているテーマについて教えてください。
私が注力しているテーマは、大きく分けて2つあります。1つは『ライフシフト』、もう1つは『知識創造理論』です。
高齢化や人口減少が進む中で、個人が自分のキャリアをどのように設計していくかが大きな課題になります。単に『自分の食い扶持をどう稼ぐか』ということにとどまらず、社会や次世代にどう貢献していくかを考える必要があると感じています。
例えば、キャリアの中でいつからどのような準備をしていくべきか、どのように目標を設定すべきかといった点は、多くの人が十分に考えられていないのが現状です。日本は経済や人口の面で縮小傾向にありますが、このまま個人が自分の生活だけに目を向けていては、社会も未来も持ちません。もちろん、自分の楽しみや生活に精一杯なのは自然なことですが、これからの時代はそれだけでは済まなくなっていくでしょう。
社会全体や次の世代を視野に入れ、自分のキャリアや学びをどう結びつけていくのかという意識が求められているのです。この問題意識は、私が立ち上げたライフシフト大学の根幹にもなっています。
きっかけとなったのは、リンダ・グラットン氏の著書『LIFE SHIFT』でした。59歳の時にこの本を読み、『人生100年時代に備え、80歳まで現役でいなければならない』という内容に衝撃を受けました。それまでの常識では『60歳で定年を迎え、悠々自適に暮らす』という感覚が一般的でしたが、あと20年働き続ける必要があるという現実には驚かされました。
この気づきから、長寿化に対応したキャリアデザインや学び直し、デジタル化への対応といった課題を体系的に学べる場をつくろうと考え、ライフシフト大学を設立しました。ここでは、時代の変化に備え、個人が主体的にキャリアを構築するための学びを提供しています。
イノベーションを起こすイノベーターシップとは
━━ もう1つのテーマである知識創造理論とは?
これは一橋大学の野中郁次郎先生と共に研究を進めてきたテーマで、『知を創造する力』、すなわちイノベーションを起こす力をどう育むかを探求してきました。私はこの力を『イノベーターシップ』と呼んでいます。
マネジメントやリーダーシップという言葉はよく耳にしますが、それらはどうしても現状の業務や組織の中で完結しがちです。しかし今の時代、それだけでは不十分です。社会や新産業の創出といった大きな視点を持ち、現状を超えて変革を起こす力こそが必要だと考えています。それが『イノベーターシップ』です。
企業においても、この力を持つ人材は圧倒的に不足しています。特にミドルマネージャー以上の層がイノベーターシップを育めなければ、企業は次第に衰退していくでしょう。日々の業務や短期的な利益追求に追われる中で、長期的な視点を持つ余裕が失われ、新しい価値が生まれなくなってしまう。この現実を打開するためにも、イノベーターシップを持つ人材を育てていくことが不可欠だと強く感じています。
大学院教育に根付くイノベーターシップ
━━ 多摩大学大学院ではイノベーターシップを教育の中心に据えていると伺いました。なぜこのテーマが重要だと考えられたのでしょうか?
多摩大学大学院では、イノベーターシップを教育の中心に据えています。MBAは通常、戦略や会計、マーケティング、組織論といった分野に重点を置き、優秀なマネージャーを育てる教育が中心です。
しかし、それだけでは社会全体を変えるイノベーターは育ちません。マネージャーとして現状をベースに発展させる力は身につきますが、まったく新しい未来を切り拓く視点や行動力は不足しがちです。
そこで私は、これからの時代に必要なのは、現状の改善を現在の立ち位置にとどまって努力するのではなく、広い視界をもって中長期レンジで未来を創造する変革を起こせる人材を育てることだと考えました。
━━ その課題に対して、どのような改革を行ったのでしょうか?
研究科長時代には、こうした課題意識からイノベーターシップを実現するためのカリキュラムの大幅な再編を行い、『イノベーターシップの実践』という講義も新たに設けました。この授業では、理論を暗記するのではなく、社会や組織に実際に変革をもたらすための思考法や視座を重視しています。
受講者には、日常業務の延長線上では得られない視野を広げ、自分の専門領域を超えて価値を創造する力を養ってもらいたいと考えています。

デジタル化とAIが変える学びと働き方
━━ AIやデジタル化が進む中で、教育や学び方にどのような変化を感じますか?
AIやデジタル化の進展によって、教育や学び方は大きく変わりました。以前であれば東京圏に住んでいなければ受けられなかった質の高い授業が、オンラインの普及によって地方や海外からでも受講できるようになっています。また、AIを活用した壁打ちや自己学習も一般化し、学びがより身近になり、まさに“学びの民主化”が進んでいると感じます。
━━ 一方で、AIが業務に与える影響についてはどうお考えですか?
AIが業務に与える影響も無視できません。単純なデスクワークはAIに置き換えられつつあり、ホワイトカラー職も安泰ではありません。
これからはAIを道具として使いこなす力や、AIの出力を評価し、修正・補完できる能力が求められます。従来のやり方に固執していては通用しない時代だからこそ、学び直しやリスキリングが不可欠になっていると強く感じています。
パイ型人材という生存戦略
━━ これからの時代に求められる人材像について、どのようにお考えですか?
私は『パイ型人材』という表現を使っています。演習率の記号『π(パイ)』のように、横棒(=幅広い教養)の下に2本以上の専門性を持った懐の深い、知識ベースの広い人材のことです。1つの専門性はOJTでも磨けますが、それだけでは変化に対応できません。業務外の学びを通じて新たな柱を増やし、多角的な視点で課題に取り組むことが必要です。
━━ 日本における自己投資や学び直しの現状については?
残業が減り自由時間は増えたものの、自己啓発に充てられる時間は年間でわずか5時間程度しか増えていないというデータもあります。『教育は会社が与えるもの』という意識が依然として強く、自ら学ぶ文化が不足していると感じます。
企業や教育機関が果たすべき役割
━━ 個人が自発的に学ぶだけでは不十分だということでしょうか?
そうですね。個人任せでは、好きなことだけを学ぶ偏りが生まれがちです。SNSでは自分に合う情報だけが流れてきますが、新聞は幅広い分野を網羅しますよね。教育機関や企業は、この『新聞の役割』を果たす必要があります。今後必要な学びを提示し、方向性や危機感を示していくことが重要です。
━━ 特にデジタル分野についてはどうでしょう?
『デジタルは苦手だからやらない』では済まされない時代です。教育機関や企業が率先して、何を学ぶべきかを明示し、個人が挑戦できる環境を整える必要があります。
フリーランスに必要なスキルと視点
━━ フリーランスやクラウドワーカーにとってのリスキリングは、どのような意味を持つのでしょうか?
フリーランスは組織に守られない分、自らの価値を高めることが不可欠です。コミュニケーション力や心理的洞察力、顧客のビジネスモデル理解といったスキルが求められます。
━━ 具体的に、どのような能力が差別化につながるのでしょうか?
情報収集力やリサーチ力が重要です。企業に属さないからこそ、業界動向や経営戦略を主体的に掴む必要があります。そうした視点があることで、単なる受注業務に留まらず、提案力を伴うパートナーとして選ばれる存在になれるのです。

学び直しが未来を拓く
━━ 最後に、これからの時代を生きる私たちに向けてメッセージをお願いします。
人生100年時代では、学び続ける姿勢が欠かせません。企業に頼るのではなく、個人が自ら投資して未来に備えることが必要です。イノベーターシップを持ち、社会や次世代に貢献できるキャリアを描ける人材こそが、日本を前に進める原動力になるでしょう。
学び直しを始めるにあたっては、大きなことをいきなりやろうとせず、小さな一歩から始めることが大切です。オンライン講座やセミナーへの参加、専門書を1冊読むといったことでも構いません。
最初の一歩を踏み出すことで視野が広がり、次の学びへの意欲が自然に湧いてきます。大事なのは『学びを止めない』ことです。
まとめ
AIやデジタル化が加速し、人口減少という現実が迫る中で、「キャリアの再設計」と「学び直し」は避けて通れないテーマです。徳岡氏の語る「イノベーターシップ」や「パイ型人材」という視点は、単なるスキルの習得にとどまらず、社会や次世代に貢献できる人材像を示しています。
学び続けることは、未来への大切な投資であり、自分自身の可能性を広げる行為でもあります。まずは小さな一歩から。現状に安住するのではなく、次の時代を見据えて前進する意識が必要になってくるでしょう。