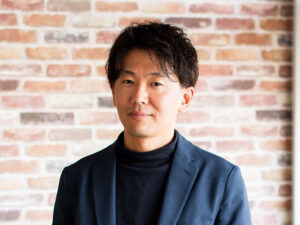立命館大学 総合心理学部 教授 高橋潔氏
AIやデジタル技術の進展、そしてクラウドワークの拡大によって、私たちの働き方は大きく変化しつつあります。その中で改めて問われるのが「人はなぜ働くのか」「どう学び続けるのか」という根本的な問いです。
高橋氏は、金井壽宏氏とともに日本に「組織行動」という学問を定着させてきた第一人者です。2024年には、代表作『組織行動の考え方』を服部泰宏氏と大幅に改訂し、リスキリングの意義を再び強調しました。
今回のインタビューでは、その挑戦と展望についてお話を伺いました。
組織行動を日本に根づかせる挑戦
━━ 『組織行動の考え方・新版』を改訂された理由を教えてください。
20年前に共著で出版した『組織行動の考え方』は、日本に「組織行動」を紹介した本でした。当時の経営学は会計や戦略など数値中心であり、「組織行動」という領域自体がほとんど認知されていませんでした。人の問題も、人事管理という名の下で管理する対象でした。ですが、実際に企業を動かし、その力を生み出すのは「人の行動」です。経営の神髄でありながら見落とされてきた部分に光を当てる――そう考えたのが出発点でした。
新版ではリーダーシップや人事評価など、自分の研究に寄せて拡充するとともに、採用やストレスやチームワークや組織文化といった、旧版では扱えなかった6つの章を書き下ろしました。領域全体を俯瞰し、組織行動の基本から応用までを体系的に学べる内容になったと思います。欧米から知識を輸入すること一辺倒で学んできたこの国で、東洋哲学からの知恵をふんだんに盛り込み、独創的な知識体系をめざしました。
今では経営面や人材採用、そして大学の科目でも当たり前のように学ばれてきて、ようやく芽が出てきたと感じています。組織行動に和洋折衷という新機軸を根づかせたいと思っています。
━━ ご専門の「産業・組織心理学」とはどのような学問ですか?
産業心理学は採用、評価、訓練、安全衛生などを扱います。組織心理学はモチベーションやリーダーシップ、職務満足、キャリア開発、組織文化などを扱います。この二つを統合した心理学分野が「産業・組織心理学」と呼ばれ、経営学では「組織行動」という名で定着しています。
産業心理学は産業界で活躍する「個人」の側、組織心理学は「集団や組織」の側を見る。両方をつなげてこそ、「働く人間」の全体像が見えてきます。それを経営現場に落とし込むのが組織行動の役割です。
━━ 日本では心理学というと臨床のイメージが強いですが?
多くの人は「心理学=臨床心理」と思いがちです。また、心理学は心を扱う学問だと考えがちです。けれど心理学はそれだけではありません。心理学が応用される場面として、医療と教育と司法(犯罪)がイメージされてしまいます。しかし、日本以外の国では、心理学を学んだ人が活躍するフィールドとしては、医療と並んで、産業と経営の場面でとくに豊かな機会があり、収入や雇用の面で有利なので人気があります。組織行動は人が働き、学び、成長する過程を支える学問でもあります。心理学とのクロスオーバーとはいえ、心理学の狭いイメージに縛られないようにしたいものです。
特にクラウドワーカーやフリーランスのように組織に属さない働き方も広がる現在、モチベーション管理やキャリア開発といった組織行動に、心理学の知見はますます重要だと考えています。
人材育成の停滞と勤勉意識の低下
━━ 日本企業の人材育成にどのような変化を感じていますか?
米国ATD(Association of Talent Development:米人材開発協会)の調査でも示されているように、アメリカでは従業員一人あたりの年間学習時間は減少傾向にあります。おそらく日本でも、同じ傾向にあるでしょう。企業の人材育成費用は横ばいか削減傾向で、研修を「未来への投資」ではなく、「コスト」と見る企業が増えています。
経営層は「DX」や「AI活用」といった“バズワード”に飛びつきますが、社員がどう学び直し、能力を高めるかという土台には関心が薄いのが実情です。DX人材やAI人材であれば、高い給料を出して、外から採ってくるしかありません。一方で、育成はOJTに頼りすぎてきたために、組織に人材を育てる力が弱まっています。
その結果、かつて評価された「日本人の勤勉さ」にも陰りが見えます。「頑張っても給料は上がらない」といった諦めが広がり、サイレント・クィッティング(=静かな退職)が増えています。
━━ こうした変化は「失われた30年」とどう関係していますか?
日本の賃金水準は1990年代からほぼ停滞しています。企業は利益を内部留保に回し、社員に還元してこなかったため、「勤勉に働けば報われる」という信念が崩れました。
さらにバブル崩壊以降、研究開発や教育投資を削ったことなどから、中途採用で「即戦力」を求める文化が固定化してきました。
━━ 勤勉さの低下は世界的な現象ですが、日本特有の課題は何でしょうか?
アメリカでもサイレント・クィッティングや大量離職はありますが、新事業が次々に生まれるため、人材は新しい挑戦の場を見つけやすい。反面、シリコンバレーでのIT技術者の大量解雇に象徴されるように、近視眼的でドライな財務視点での人事管理もなされています。一方日本は、AIや電気自動車、バイオ医療や再生可能エネルギー、キャッシュレス金融などの新分野で事業創出に遅れをとり、海外から学ぶ努力も不足していると感じます。
典型例がロボット工学です。かつて世界をリードした日本は今や中国に抜かれ、採算が取れない研究投資を打ち切った結果、人材も流出しました。一企業で収支を考えたり、一大学で細々と研究開発を行うという閉じた考え方では、新産業への投資はうまくいきません。地域や国全体で人材と成果を融通し合う、産業のエコシステムという視点が必要です。
働く個人のほうでは、日本の課題は「勤勉さが薄れた」ことだけでなく、「努力が報われる仕組みや挑戦を受け止める基盤をつくれなかった」ことにあります。これを変えるには、教育投資を百年の計ととらえ、勤勉さを「長時間労働」ではなく「創造性と挑戦意欲」と再定義し、企業や大学や政府が未来像を示すことが不可欠です。

リスキリングと教育機関
━━ リスキリング推進のために必要な条件は何でしょうか?
OJTは即効性があり有効な面もありますが、AIや量子コンピュータのように高度で専門的な分野には対応できません。現場経験だけで自然に身につくものではなく、企業が大学や研究機関と往還する体系的な教育が不可欠です。しかし日本企業は「現場で学べば十分」というOJTに則した考えに偏りがちで、リスキリングを推進する環境が未発達です。
企業は自分たち組織の将来だけではなく、産業の将来にも目を向ける必要があります。未来への方向性を示し、“日銭を稼ぐ部分”と“将来への投資部分”との二階建て構造が求められます。いまの必要だけを考えれば、未来はやがて老後に変わり、ジリ貧になってしまうでしょう。お金のあるうちに、余裕をもって明るい未来の根っこを作っていく必要があります。
そして、大学のような教育機関は単純に教育プログラムを実践だけするのではなく、何を学べば良いのか定めて、人材育成の将来像などを示す必要があるでしょう。先細る18歳人口に迎合して、ウケのよい学部を設置したり、現存教員の配置を優先した方針で、未来を見つめても、教育機関の延命にしかなりません。
『米百俵』精神の祖師である小林虎三郎氏の「教育こそが最終的には地域を繁栄させ、人々の生活をよくする」といった教えに立ち返り、教育を百年の計とする発想が欠かせません。最短でも百年先を見て発想するくせを、人々がもつことが大事です。
リスキリング、リカレント教育と学びの再設計
━━ 教育を進める上で、日本が直面している課題は何でしょうか?
日本では「リカレント教育=社会人対象」とか、「社会人教育=MBA」などといった狭くて固まった発想が根強く、窮屈です。体系的な学び直しの仕組みが必要ですが、従来の知識伝授型教育では急速な技術革新に対応できません。必要なのは、自己学習(セルフラーニング)に加えて、複数人での学び合い(ピア・ティーチング)や反転授業など、主体的で協働的な学び方です。
また、『負うた子に教えられて浅瀬を渡る』という言葉があるように、若い世代の感性やデジタルスキルから学ぶ姿勢も重要です。小中学生の小さい子どもたちからも教えを乞うくらいの柔軟な発想でリカレント教育を考える必要があるでしょう。
━━ AIや海外の事例はどのような影響がありますか?
AIは学びの伴走者として機能し、学習計画や教材提示を通じて個々の学びを支援できます。AIの基盤モデルを作るには、アメリカや中国に遅れをとっていますが、応用するアプリケーションであれば参入余地はあるので、そこに積極投資することは大事です。
さらに、中国のAI戦略(DeepSeekなど)や欧州のリカレント教育政策のように、国家レベルで仕組みを整える姿勢からも学ぶべき点が多いと感じています。特に中国は安全保障上の問題で、関わらないようにするといった政治的風潮がありますが、技術面で学ぶことは非常に多いので、真摯に教えを乞う姿勢が大事だなと思います。飛鳥時代から、遣隋使や遣唐使を通して、中国に学んできた歴史を思えばなおさらです。
キャリア形成と研修効果の測定
━━ リスキリングは個人のキャリアにどのような意味を持つのでしょうか?
リスキリングが、単なる個人のスキルの積み重ねに留まってしまえば、得るものは少ないでしょう。自分が学んだ知識をみんなと共有して、集団として知識や技術が集積して、そしてはじめて力を持つのです。知識やスキルというのはみんなとともに共創することで、自分にも帰ってくる。他者と共有することで、クラウドワーカーにとっても様々な機会創出の可能性が出ます。学びは「利己」のためだけでなく、「利他」にもつながるものです。
企業側の体制として、研修の満足度だけ評価するのでは不十分です。学習の定着、行動の変化、組織成果まで測るカークパトリックの4段階モデルが有効です。さらに財務成果に加え、顧客満足や成長といった視点でも教育効果を測定できます。教育は「コスト」ではなく「投資」であり、その回収を経営戦略に結びつける必要があります。
━━ 今後のリスキリングの方向性はどのようになるとお考えですか?
これからは「多様化」と「国際化」が鍵です。日本は欧米モデルに偏ってきましたが、中国やインド、アフリカなど様々な新興国から学ぶ姿勢が必要です。先進国という枠にはまり、新興国に対して無意識に優越感をもってきたかもしれませんが、その枠が外れた先に、新たな学びの地平が見えてくるはずです。
また、翻訳や音声認識の進化で言語の壁が低くなり、海外の知識や情報に直接アクセスできるようになっています。自ら一次情報を取りに行き、俯瞰してものを見る鳥の目を持ち、多様な知識を吸収することが求められるでしょう。

クラウドワーカーへのメッセージ
━━ クラウドワーカーにとってリスキリングはどのような意義を持つのでしょうか?
クラウドワーカーは一人で仕事をしているように見えても、実際には社会のネットワークの中で生きています。学びを「共有」して、集団で知識や技能を集積してこそ力を持ち、自分のスキルを仲間に還元することで、仕事の幅や支援の輪が広がります。
学びは終わりのない旅です。シェイクスピアが『知恵は天に飛ぶ翼である』と述べたように、学びは自由と未来をもたらします。クラウドワーカーは自由な働き方を選んだ分、自分でキャリアをデザインする責任を負っています。そのためにも、年齢や経験に関わらず常に自分をアップデートする姿勢が必要です。
黒澤明監督『七人の侍』で語られるセリフがあります━━「人を守ってこそ、自分も守れる。己のことばかり考えるやつは、己をも滅ぼすやつだ。戦とはそういうものだ。」━━これは “利他のこころ” を表しています。『情けは人の為ならず』ということわざがあるように、自己を越えた全体の利益を考えることが、巡りめぐって自分の利益につながることを知る必要があります。
リスキリングは「生存戦略」であると同時に「未来を創る戦略」です。自由と柔軟性を持つクラウドワーカーは、真の利益を見据えて、ぜひ「利他のこころ」で学びを社会に還元してください。そうすることで、クラウドワーカーは単なる個人事業主ではなく、社会の未来を切り開く主体にもなれるでしょう。
まとめ
学び直しは、一人ひとりのキャリアを強くするだけでなく、組織や社会を変える力を秘めています。
リスキリングによって得られるのは、新しい知識やスキルだけではありません。挑戦する勇気や他者と協働して生まれる力こそが、未来を切り開く原動力になります。
変化の大きい時代だからこそ、俯瞰の目を持ち、学びを止めず、自らを更新し続ける姿勢が何よりも大切になるでしょう。